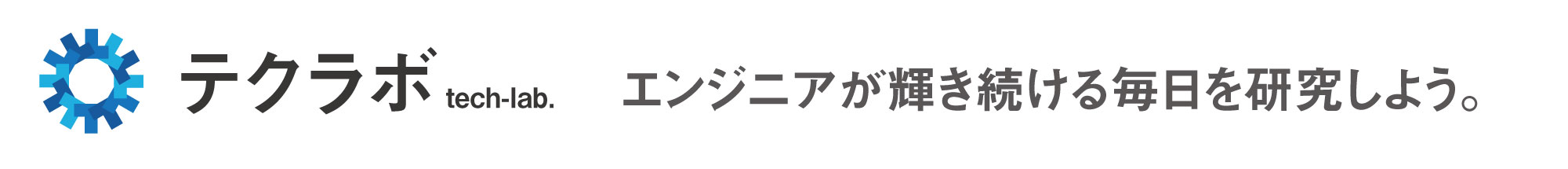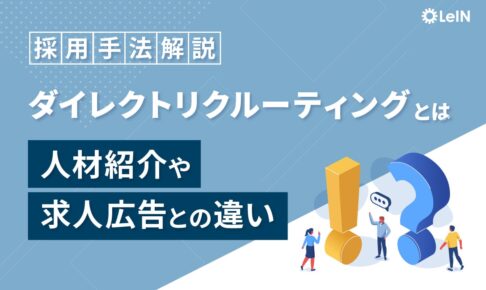こんにちは、レインエコノミックグラフ研究所の山口です。
皆様は、「採用オウンドメディア」という言葉を聞いたことがありますか?
人事担当者の方であれば、採用オウンドメディアの活用事例を目にしたことがある方もいるかと思います。
「採用オウンドメディア」とは、企業の採用に特化した社内情報を発信するメディアのことです。
本記事では、採用オウンドメディアの概要、採用オウンドメディア運営による利点、及び採用オウンドメディア運営とリファラル採用について執筆します。
目次
①採用オウンドメディアの概要
②採用オウンドメディア運営による利点
③採用オウンドメディア運営とリファラル採用
①採用オウンドメディアの概要
前述の通り、「採用オウンドメディア」とは、企業の採用に特化した社内情報を発信するメディアのことです。
IT系の「メガベンチャー」と呼ばれる企業の大多数は、採用オウンドメディアを運営しています。
例えば、下記は有名なIT企業が運営する採用オウンドメディアの一例となります。
- リクルートグループの「meet group」
- 株式会社サイバーエージェントの「 FEATUReS 」
- 株式会社メルカリの「mercan」
- 株式会社ディー・エヌ・エーの「フルスイング」
- 株式会社Gunosyの「Gunosiru」
- 株式会社マクロミルの「ミルノート」
- 株式会社SmartHRの「SmartHRオープン社内報」
- LINE株式会社の「LINE HR BLOG」
- ヤフー株式会社の「linotice」
採用オウンドメディアでは、主に下記の3つを主軸に記事を書くことが多いです。
【会社・事業】
会社の概要・沿革・カルチャー・教育指針や、事業の詳細など、社員以外には見えづらい企業の内側を発信することで、会社に興味をもつあらゆる層の読者に有益な情報を提供することができます。
【社員】
社員に対するインタビューや社内活動などの取り組みを発信することで、現社員の入社理由、モチベーション、日々の業務の詳細など、候補者となりうる読者に最適な情報を提供することができます。
【ニュース】
自社のプロダクトやサービスに関する最新情報、(採用などの)イベント告知、業界全体のニュースを発信することで、業界に興味を持つ読者間によって共有されやすい最先端の情報を提供することができます。
②採用オウンドメディア運営による利点
有名IT企業が採用オウンドメディアを運営するのはなぜでしょうか?
背景には、「年功序列制度」「終身雇用制度」「新卒一括採用」といった既存の制度が壊れつつあることが挙げられます。
現在では、会社に不可欠な能力を有していれば新卒でも1,000万の報酬を払うこともあれば、入社後1-3年で辞めてしまうことも当たり前になり、また関連して、中途採用を行うことが不可欠となっている企業も増加しています。
このトレンドは特にIT業界にとって顕著で、最先端の技術を有するエンジニアの採用を行う場合、採用ブランディングが不可欠となります。
(関連:LinkedInを活用した採用ブランディングの体制構築・戦略策定 )
採用オウンドメディアを運営することで、直接「採用ブランド力」を増加させることが可能となるため、有名IT企業の大半が採用オウンドメディアを運営しています。
採用オウンドメディアを運営する上で、特に顕著な利点は、下記の3点となります。
1. 能動的候補者が増加する
採用オウンドメディア運営における最大の利点が、能動的候補者が増加することです。
会社の事業指針、カルチャー、福利厚生など、また提供するサービスやプロダクトなどが候補者に刺さるものであれば、その事実を発信することで、自ずと候補者が集まってきます。
特に、最先端の情報に関して常にレーダーを張っているエンジニアは常に業界のニュースを積極的に取り入れているため、採用オウンドメディアの運営は有益となります。
会社側からアプローチしなくても候補者が増えるということは、優秀な人材の絶対数がプール全体から増加するだけでなく、採用コストの低下にも繋がります。
2. 潜在的候補者へのアプローチが容易になる
採用オウンドメディア運営における次点の利点が、潜在的候補者へのアプローチが容易になることです。
上記同様、会社の内部情報を発信することで、能動的に転職先を探している層以外の読者にも会社の良さを伝えていくことができます。
会社側から候補者にアプローチする際、潜在的候補者が採用オウンドメディアの記事を目にしていたかどうかで、返信率に差が出てくることは明白です。
例えば、採用ブランディングをいち早く取り入れ、社会一般まで浸透させているGAFAのような外資系IT最大手からポジションの誘いがあれば、今転職を考えていなくても、その採用ブランド力に惹かれ、少し話を聞いてみようと思ってしまう人が少なくないはずです。
3. 入社後の企業文化のミスマッチ減少
最後に、採用オウンドメディア運営における利点の一つとして、 入社後の企業文化のミスマッチが減少するということが挙げられます。
採用オウンドメディアを通し、候補者が会社の事業指針、カルチャー、福利厚生だけではなく、社員の実際の一日の流れや仕事の詳細、モチベーションなどの情報を事前に把握している場合、入社後の「え、こんなはずじゃなかったのに…」といったギャップに遭遇する確率が減少します。
ギャップの減少はそのまま離職率の減少に繋がるため、長期的に採用コストが低下するだけでなく、社員と社風のマッチによるシナジーまで期待することができます。
③採用オウンドメディア運営とリファラル採用
最後に、採用オウンドメディア運営とリファラル戦略について執筆したいと思います。
以前、リファラル採用について記事を書き、「採用コストの低下」、「転職潜在層へのアプローチ」、「企業文化のミスマッチ防止」という利点があることを述べました。
上述の採用オウンドメディア運営の利点である「能動的候補者が増加する」、「 潜在的候補者へのアプローチが容易になる 」、「入社後の企業文化のミスマッチ減少」(そして、複合的な採用コストの低下)を見てみると、リファラル採用の利点と酷似していることが分かります。
採用オウンドメディア運営を運営しつつ、リファラル制度を採択することは、シナジーに繋がると言えます。
事実、株式会社メルカリ小泉氏は、日経ビジネスのインタビューで「mercan」を例に取り、会社のミッションやバリューを候補者へ共有することの大切さを説いています。
小泉氏は、「リファラル採用でターゲットを決めるのも、会社の魅力を伝えるのも、全てミッションとバリューが軸になっているから1本の筋が通る。」と語っています。
ビジョン・ミッション・バリューなどを明文化し、採用メッセージを添えて情報発信・拡散することは、採用オウンドメディアにおいてもリファラル採用においても同じプロセスとなります。
採用オウンドメディアをまだ運営していない、もしくはリファラル採用をまだ取り入れていない企業の人事担当者の方は、是非どちらも同時に検討し、採用ブランディングを強化することだけではなく、そのプラットフォームを活かし、社員にしっかりと共有することで、リファラル採用にまで繋げてみてください。
お問合せはこちらまで
もっと詳しくサービスを知りたい。自社の採用状況にLinkedInが合うのか相談したい。など、LinkedInが気になる方は是非、ご相談ください。
【LinkedIN、LeINに関する問い合わせページ】
▼株式会社レインエコノミックグラフ研究所(HP: http://www.lein.co.jp/ )
『LeIN(レイン)』はLinkedInオフィシャルパートナーとしてLinkedIn製品とHRコンサルティングサービスを提供し、顧客の事業成長を支援する会社です。LinkedInをはじめダイレクトリクルーティング(DR)を活用する企業を増やすことで、日本の採用マーケットにDRを普及・浸透させることをミッションとしています。特にITエンジニアの採用支援を得意としています。